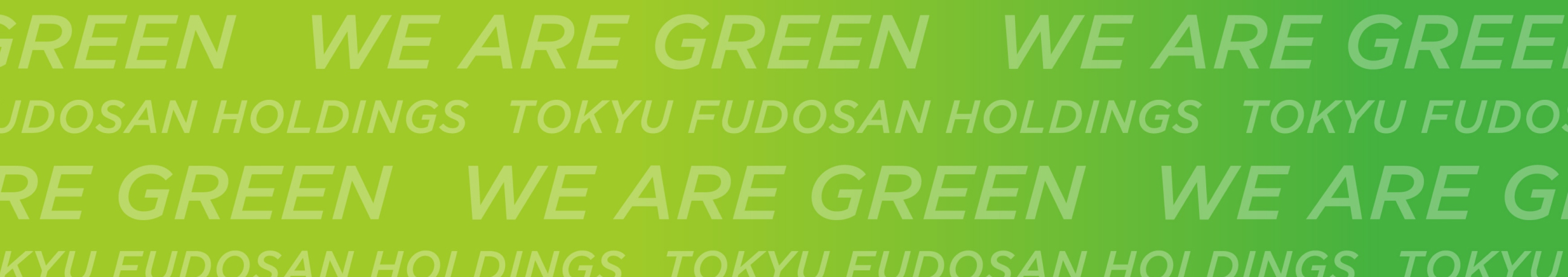
COMPANY INFORMATION
社外取締役座談会
中期経営計画2030へのコミットメントと評価
前中期経営計画の成果を基盤に、
強靭化フェーズの第一歩へ
新たに発表した中期経営計画2030。
どのような議論を経て策定に至り、社外取締役として策定にどうコミットし評価をしているか、
また、中長期的な未来への期待と課題感について、自由闊達な意見交換を行いました。

2025年7月8日実施
中期経営計画2030の評価
—中期経営計画2030の策定プロセスにどのように関わりましたか。また、計画の内容についてはどう感じますか。
貝阿彌
策定の過程で我々も複数回ドラフトに意見を述べる機会があり、そのたびに修正が加えられました。例えば、事業ポートフォリオマネジメントの説明原案に理解しづらい部分もありましたが、外部にもわかりやすい表現で、との意見も反映し、最終的には各事業の市場成長性と競争優位性の2軸で定点観測していく方向性が示され非常にわかりやすくなりました。社内・社外の視点で議論を尽くしまとめあげた点を評価しています。また、2030年度の営業利益目標は2,200億円と、2021年の長期経営方針発表時の目標から約1.5倍に上方修正しています。この背景には、不動産流通事業の順調な伸びのほかに、再生可能エネルギー事業と海外事業の成長性を見込んでいるものだと理解しています。再生可能エネルギー事業については、社会課題の解決にもつながるという点で特に注力すべきだという意見は継続的に述べていたので、「GXビジネスモデルの確立」として重点テーマに位置付けられたのは良かったと考えています。

法務省大臣官房訟務総括審議官、東京家庭裁判所所長、東京地方裁判所所長などを歴任。コンプライアンスに関する豊富な知識と経験を有する。2018年より現職。
三浦
取締役会では皆さんそれぞれの思いを述べ、社内外から多くの意見を吸い上げました。その結果、社会課題の解決を中心に据えた、未来志向の計画にまとまっていると感じます。
前中計を振り返ってみると、数値目標を2年前倒しで達成できた大きな要因は、事業ポートフォリオの見直しによる構造改革にあると思っています。各事業がそれぞれ強靭なビジネスモデルになり、さらなる成長に向けた基盤ができたと認識しています。こうした前中計の再構築フェーズでの成果を活かし、新中計では各事業で高い収益を生み出す数値目標を掲げるとともに、長年の懸案だったD/Eレシオも2030年度目標で1.8倍以下としています。こうした事業的にも財務面でもバランスの取れた計画になっていると感じます。
星野
お二人がおっしゃるように、構造改革を経て、当社グループの各事業において一定の競争優位性が備わっています。それらを上手く活用しながらどの分野に注力するか、どのような社会課題解決に貢献していくかという文脈で何度も議論してきたことで、計画自体がロジカルでわかりやすくなっていると思います。新中計を支える要素として私が注目しているのは、DXです。社員のDXに対する意識も変わってきており、業務効率化などの面で一定の成果が出ていますし、さまざまなソリューション展開によりCXの向上にも貢献しています。ビジネスモデル変革を支えるDXという重要な位置づけで、本中計でも整理されたことは評価したいと思います。

大蔵省(現財務省)に入省後、金融庁の設立などに携わったのち、主税局長、国税庁長官などを歴任。2021年より現職。
定塚
本当にかなりの時間をかけて議論してきましたが、新中計は当社グループの競争優位性が最大限に活かされた「攻め重視」の計画になったと感じます。広域渋谷圏では、これまで培ったまちづくりノウハウが活かされますし、グローカルビジネスでは、ホテル・リゾート事業での経験から地域の人や産業と密接にかかわるビジネスの創出にも強みがあります。また、GXビジネスモデルの確立においては、太陽光から風力、水力と、多彩なエネルギーへの取り組みを組み合わせ、今後の拡大が期待できます。
取締役会でもESGについて議論になりますが、ESGへの取り組み方針を世に伝わるように打ち出していくのが大変重要と思っています。
宇野
私は2024年に社外取締役に就任したので、新中計の策定においてはより外部の視点を意識しながら意見を述べました。他社との策定プロセス上の違いとしては、実際の担当者が中計の戦略を説明してくれたのでより理解が進みましたし、細かい部分まで納得のいく答えがあったのは良い点でした。
私は新中計冒頭のステートメントにとても共感できたので、具体的にサービスを享受するステークホルダーの皆さまにも理解してもらい、当社グループが社会にとってなくてはならない存在であると感じていただくことが、本中計の本質的な目的であると考えています。実現に向けたロードマップは社会情勢に応じて軌道修正しながら、ステートメントが掲げる世界観はブレないように進んでいただきたいと思っています。
企業価値向上に向けた取り組み
—資本効率や成長性を重視した事業投資、財務改善における課題感や期待についてはいかがでしょうか。
貝阿彌
株主還元方針として、2025年度からの配当性向を35%以上に引き上げるとともに、累進配当を導入しました。現在では同業他社と比べても遜色ないレベルに達していますが、数年前まで配当性向も利回りも低く見劣りするような状況でした。今回の株主還元方針の内容は非常に大きな進歩で、投資家からも高く評価されるだろうと思っています。
また、PBRについても1倍に近い数値まで向上してきていますし、ROEも2030年度の目標である10%以上は十分に達成できる位置にいると考えています。
三浦
貝阿彌さんがおっしゃるように、企業価値を測る指標はすべて向上してきており、財務規律も含めてバランスがとれてきたと思っています。配当性向については、同業他社に比べるとまだ低いのではないかという意見も聞こえてきますが、個人的には、配当性向だけではなく、お客さまや従業員、地域社会などステークホルダー全体を俯瞰して見ることが大事だし、会社の成長投資も重要だと考えます。

日本電信電話(株)(現:NTT(株))の社長などNTTグループの要職や、(一社)日本経済団体連合会の副会長などを歴任。持株会社の経営経験者として、豊富な見識を有する。2021年より現職。
星野
新中計では、財務資本戦略がどのように企業価値向上へとつながるのか、構造を分解しながら緻密に設計されていると感じています。PBRやROEの数値については、不動産業界への追い風を考慮するとまだまだ向上の余地があるのではないかという印象で、PBR、ひいては株価を向上させるためには「将来の成長性に対する期待値」をどれだけ上げられるかが重要になってきます。その点については、各事業の将来的な収益性をいかに説得力を持って説明できるかがカギと考えます。
人手不足などのリスクが顕在化してきているなかで、グループ総合力を駆使して外部環境の変化に柔軟に対応し、ビジネスモデルの耐久性を高めることで安定的な成長につながるというストーリーをしっかりと説明してほしいと思います。
人的資本経営の現状と課題
—中期経営計画2030における人財・組織風土の位置づけや強化施策への評価はいかがでしょうか。
定塚
新中計において、人的資本経営を中核的な重要項目として位置づけた点について、評価をしたいと思います。新中計の人財戦略では、「3万人が成長し続ける人財ポートフォリオ」の構築を掲げていますが、当社グループは事業会社によって扱っている事業や業務内容が大きく違います。それぞれの事業会社での成長戦略は、ホールディングスの中計のもとで考えていくと同時に、その戦略を実現するために必要な人財ポートフォリオについては、事業会社とホールディングスが一体となって描き、実現していくことが重要だと思っています。
なかでも、私が注目したいのは、ダイバーシティと女性活躍です。2025年6月から女性役員が増加し、取締役と監査役に占める女性の割合が29.4%まで増えてきたのは大変喜ばしいことです。ただし、各事業会社での女性管理職比率については課題が残っていますので育成・研修やコミュニケーションを活発化させ、さらなるダイバーシティの深化を進めてほしいと思います。

厚生労働省や内閣府などで、働き方改革、女性活躍などを推進。行政官としての専門的知識と長年にわたる経験を有する。2021年より現職。
宇野
新中計実現に向けては、各事業をひととおり経験した社員を育成し、人財プールをしっかりとつくっていく計画を立てています。私は、グループ会社の女性管理職の方々との意見交換会に参加しており、彼女たちから各社の仕事の違いや課題感などを聞いているのですが、そこで実感したのは、個人のポテンシャルの高さに比べ、グループ全体を俯瞰する視野の広さを十分に養えていないという現状です。グループ横断的な研修などを通じて、各事業における知見やノウハウを吸収しながらスキルアップできる機会や仕組みをつくっていく必要があると思います。
貝阿彌
宇野さんのご指摘のとおり、新中計で掲げる事業変革人財の育成において大事なのは、会社・事業を越えた「越境経験」の有無です。事業会社間での異動や出向などが当てはまりますが、これらの施策は、グループの横のつながりを強めるという意味でも、あるいは個々の社員の成長にとっても非常に良い取り組みです。今後さらに人財交流を加速させ、越境経験のある社員の拡大にも注力してほしいと思っています。
定塚
新中計の人的資本経営のもう一つの柱である、組織風土改革も重要です。優秀な人財を採用・育成しても、根っことなるような組織風土が悪いとその能力は発揮できませんし、結果として定着しません。組織風土改革の重点施策として「心理的安全性の向上」を掲げていますが、心理的安全性が担保されると、一人ひとりが新たな挑戦を実行しやすくなり、最終的にイノベーティブなカルチャーの醸成につながると思います。ここに居たい、入りたいという会社を作るのが第一ですから、人材不足という大きな経営課題と併せ、しっかりと議論し進めていく必要があると思っています。
宇野
「心理的安全性の向上」は、言うは易しで難しいことなのですが、マネジメント層がマイナスの情報でも喜んで聞いてくれるという風通しの良さは無くさないでいただければと思います。また、グループ会社の人財育成にはまだまだ課題が残っています。個社最適で考えるのではなく、当社グループ全体でその社員をどう育てていくかという考え方のもと、個人のライフステージに合った仕組みや制度を整えていく必要があります。先ほど貝阿彌さんがおっしゃっていた越境経験のように、当社グループにはさまざまな業種・業態があるので、グループ外への転職ではなく、グループ内での転職が選択できる環境づくりも重要だと考えています。
2030年に向けて
—中期経営計画2030の着実な遂行やありたい姿の実現に向けて、提言すべき点や課題感はありますか。
宇野
「GXビジネスモデルの確立」という重点テーマは、当社グループの今後の成長における重要ポイントですが、なかなか投資家の皆さまに理解が浸透していないという点が課題だと思っています。GXビジネスモデルを確立することでどんな世界をつくりたいのか。それを端的に示してもらえるとより分かりやすくなると思います。これは、「グローカルビジネスの拡大」においても同じことが言えます。個々の施策だけではなく、最終的にどんな世界観をめざしているのか立体的に示すことで打ち出した施策の意義が理解もされやすくなるのではないかと思います。

(株)資生堂における業務や同社常勤監査役としての職務を通じて、リスクマネジメント、人財戦略、DXなどに豊富な知識と経験を有する。2024年より現職。
定塚
おっしゃる通りで、それは投資家の皆さまだけでなく、従業員に対しても同じだと思います。新中計の戦略と自分の仕事がどうつながっているのかがわかるように説明しなければ、具体的なアクションへと結びついていきません。例えば、重点テーマのそれぞれに対して、自分の仕事のこんな部分が貢献していると示したり、自分の仕事でどうやって貢献したいのかを自ら考えてもらったり、従業員への説明は特に工夫してやっていく必要があると思います。
三浦
新中計への理解浸透は、社内外に対してまだまだ不十分な部分があります。例えば、当社グループの再生可能エネルギー事業が日本ではトップレベルの発電能力を有し、今後の利益成長においても最も貢献度の大きい分野であるという点や、赤字の状態の海外事業をどうやって黒字に転換していくのかをより具体的に訴えていく必要があると思います。当社グループの特徴が理解され市場の認識とのギャップが解消されれば、株価にも反映されると思います。引き続きIR活動も非常に重要な要素だと捉え、取り組んでいただきたいですね。
貝阿彌
現状、海外事業は利益貢献できていませんが、2030年度の目標では営業利益が100億円にまで増加する見込みです。「本当に実現できるのか?」という問いに対し、達成に向けたロードマップについて説明していく必要がありますね。
星野
その通りですね。やはり、「将来の成長性に対する期待値」をどれだけ上げていくか。ここに議論が収れんすると思います。海外事業と再生可能エネルギー事業の収益性の向上については、もう少し分析の解像度を上げて説明をしていく必要があると思います。
再生可能エネルギー事業においては、アセット事業だけでなく、O&Mなどのノンアセット事業も強化し強靭なバリューチェーンを構築しなければ収益の拡大は見込めませんし、不動産業との相乗効果についてもより具体的な説明をしていく必要があるでしょう。また、海外事業については、従来の住宅バリューアド中心のビジネスから、物流事業などにも投資していく計画です。より具体的な道筋を示すことで社内外からの期待値を向上させ、新中計の着実な達成と企業価値の向上につなげてほしいと思います。
新任社外取締役メッセージ

日本ハイアット(株)における、日本・ミクロネシア地域の人事・総務担当のリージョナルヴァイスプレジデントとして培った知見や会社経営の経験を有する。2025年に社外取締役就任。
東急不動産ホールディングスには、不動産開発や運営を通じ、周辺コミュニティにも新たな価値やスピリットを吹き込んでいく機動力と発信力を強みとするまちづくり企業という印象を持っています。エネルギー・環境などの社会課題にもいち早く目をむけ、企業の成長とともに豊かで持続性のある世界を見据えた歩みは、当社がめざす「誰もが自分らしく、いきいきと輝ける未来」を着実に実現へと導いていくものと期待しています。
これまで私はホテル運営会社で新規開業事業などに携わり、非日常の空間とサービスを通じて提供する顧客体験価値の向上を常に意識してきました。顧客起点の発想は、価値観の多様化と市場競争の激化が進むなか、当社グループ事業においても今まで以上に強く求められる視点となるでしょう。さまざまなステークホルダーに響く新たな価値創造のため、そして社会からの支持と信頼を得る企業であり続けるため、経験を活かして貢献したいと考えています。